
敷島にお艶観音松林

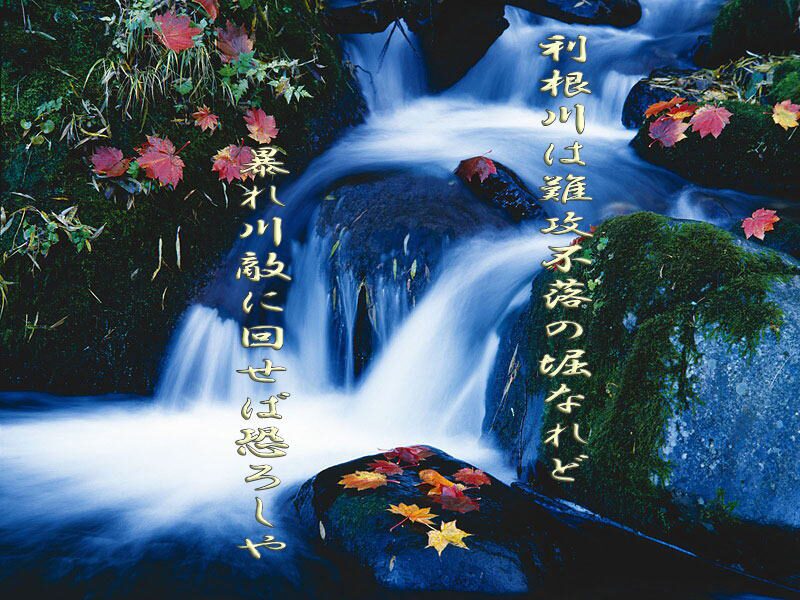
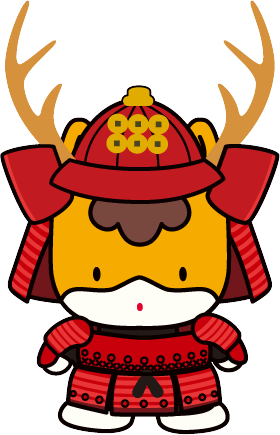
©︎群馬県 ぐんまちゃん 00552-02
 惜しいのう総社に水さえあればのう 惜しいのう総社に水さえあればのう | |
| 関ヶ原武功の陰に田地荒れ | 水路掘り利根の真水を我が村に |
| 黄金の稲穂を総社に実らせん | 新藩主秋元長朝決断も |
| 川低く高きに水引く難工事 | 取水口白井藩主も首傾げ |
| 名にし負う井伊直政も匙を投げ | 無理申せ雲に梯子は架けられまい |
| 聞いたかい我が殿様の大風呂敷 | なんでもさ田んぼに大水引くそうだ |
| 石高もグーンと増えるともっぱらだ | 冗談は休み休み言ってくれ |
| よく見ろよ利根の流れは目の下だ | 川ってのは上から下へ行くもんだ |
| いやだから白井の上から引くんだよ | なんだとう食うのがやっとだ今だって |
| だけどもよ年貢は三年取らねえと | |
| おらが殿隣の殿にやめとけと | ほんとかいよそから言われりゃ悔しいね |
| 見上げりゃあ古墳が多いな総社には | 関東も一目千里の総社だね |
| 本当だ村の自慢だ古墳群 | まったくだ水さえありゃあいいとこだ |
| 井伊様が雲がどうこう言ったとか | ああ確か雲に梯子は架けられまい |
| 国分寺七重の塔はすぐそこだ | 雲にまで立派な塔が立ってたよ |
| 考えりゃタテかヨコかの違いだけ | 植木堰架けてやるかい雲の上 |
| まあ待てよ勇ましいのはいいけどよ | もうちょっとよく聞きてえなその話 |
| 我が殿も先刻承知だ暴れ川 | そりゃそうだ坂東太郎っていうほどだ |
| 三本の暴れん坊の長兄だ | そういやあ殿は深谷にいたそうだ |
| 忍城の水攻めの話知ってるかい | 三成が川せき止めたって話だろ |
| 高松城二匹のドジョウ狙ったか | 急かされて知恵者三成焦ったね |
| 即席の石田堤も効き目なく | 反対に忍の浮き城名を上げた |
| 豪雨降る夜半に堤を壊してよ | 豊臣軍攻めてる方が飲まれたよ |
| ソロバンが暴れ川に負けたのかい | ああ利根には勝てねえ誰だって |
| 忍城に兵はどんだけいたんだい | 小田原へ主力はみんな行っちゃった |
| 兵五百領民足しても知れてらあ | 寄せ手はさ雲霞のごとき二万だよ |
| 無理ねえな降伏します開城も | いやそれが小説よりも奇なりだよ |
 忍城は沈まぬ城よ目にも見よ 忍城は沈まぬ城よ目にも見よ | |
| 天下軍降伏迫る軍使がよ | 太閤になんと甲斐姫差し出せと |
| 虎の尾をうっかり踏むとはこのこった | 緋縅の甲冑姿も眩しけり |
| 甲斐姫は美形の上に武芸よし | |
| でくのぼう世間じゃ陰で言うけどさ | のぼう様堪忍袋の緒が切れた |
| ご覧あれ田楽踊りは船の上 | 足下の不如意は天の加勢なり |
| でかい象沼地じゃ浮かんでいられまい | 騎馬武者も蹄が立たなきゃ武者人形 |
| とっておき泥饅頭を食わしたる | 足らざれば鮎か山女魚か槍御膳 |
| 忍城は小田原落ちても浮いていた | |
| 深谷から目と鼻の先だ忍城は | 利根川の猛威は殿の原点だ |
| 我が殿の偉いところはそこなんだ | 白井から総社の地形をコツコツと |
| このいくさ勝ち切るために先ず地積 | 敵を知り己を知ればってやつだねえ |
| 夜もすがら測量提灯揺れていた | 秋元公豪胆にしてぬかりねえ |
| 領民を思う気持ちがありがてえ | 我が殿についていきゃあ間違いねえ |
| よし決めたみんなで土を掻き出すべえ | |
| 三年の苦難の開削成し遂げて | 錦秋の総社に実る五千石 |
| 鍬ふるいモッコで運んでタコで突く | 難工事蛸胴突きの語句を知る |
| イラストが辛い労働物語る | |
| 美しき甘楽町の雄川堰 | 文武の地箕輪城の長野堰 |
| 我が村の世界遺産の灌漑も | 伝説の天狗の助けあればこそ |
| テコあれば地球も動くというものの | 村人がハタと手を止め固まった |
| もうダメだビクともしねえこの岩は | 茫然と大岩見上げて立ち尽くす |
| ホントだな雲に梯子はかけられねえ | 我が殿の武州の平地はいざ知らず |
| この辺は噴火の岩の通り道 | もうよすべえ山の神だってお怒りだ |
| 殿様に見てもらうべえこの難儀 | |
 古来より護国の神が座す神地 古来より護国の神が座す神地 | |
| こうづけの総社神社は総鎮守 | 厄祓い地鎮の祭祀をおごそかに |
| 我が領主神社に籠り願を懸け | |
| 岩砕き命の水を与えたまえ | この村を利根の清流で満たしたまえ |
| 願が明け祈りが天に通じたか | 忽然と現場にひとりの山伏が |
| 行き詰まり途方に暮れる村人に | たくさんの薪と水とを用意せよ |
| 岩に置き薪をひたすら燃やすのじゃ | その岩が十分熱くなったらば |
| 間をおかず一気に水をかけるのじゃ | そうすれば割れるであろういくつかに |
| 村人は半信半疑になりつつも | 山伏になんかオーラを感じるぞ |
| 物事はやってみなきゃわかんねえ | 山伏に言われた通りやってんべえ |
| 本当だ岩が割れたぞこりゃすげえ | 世の中はこんな奇跡が起きるのか |
| よしこれでやっと引けるぞ利根の水 | ありがてえあれ山伏は何処行った |
| 岩が割れ喜びに沸く村人が | 山伏に熱く感謝を言おうにも |
| 忽然ともうその姿消していた | 山伏は榛名の天狗にちげえねえ |
| 困ってる俺たち助けに来たんだよ | この恩は石に刻んで残してえ |
| 三年後みんなの苦労が報われて | 乾いてる総社の城下に水が来た |
| 舞い降りた天狗に感謝を捧げつつ | 我が誇り名を天狗岩用水に |
| これからは腹いっぱい食えるんだ | 村巡る我が五千石用水だ |
| 末代の総社にずっと流れるぞ | 良かったなあ秋元様に付いてきて |
| 空浮かぶ雲に梯子を架けたぞお | 殿様の顔が立ったのも嬉しいなあ |
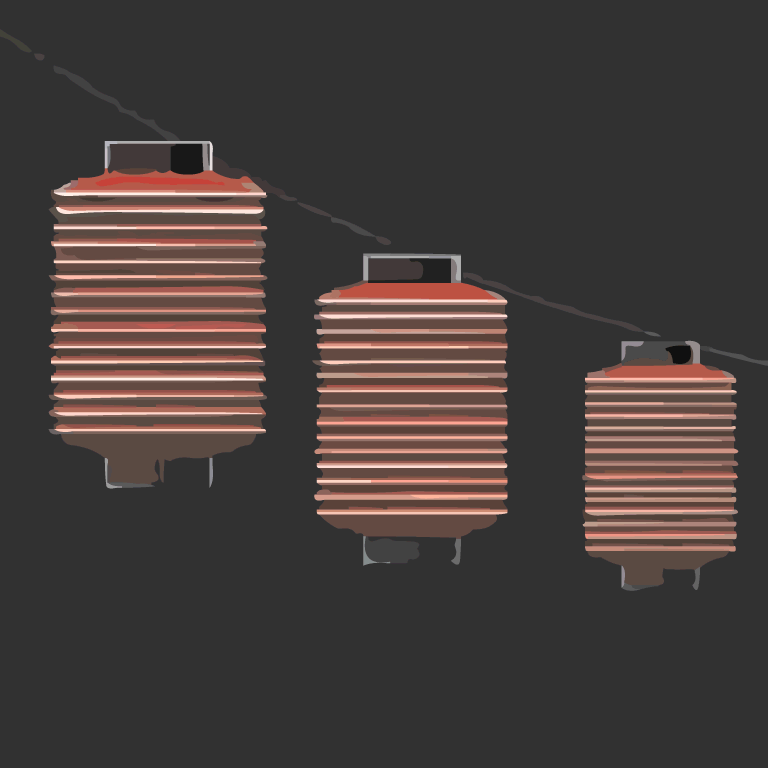 暗闇に光の水路がいち早く 暗闇に光の水路がいち早く | |
| この快挙丁間稲荷のお陰だよ | ありがたく参拝しようぜみんなして |
| 風情ある社が鎮座問屋町 | ヒラヒラと小高い山に幟旗 |
| 神の使者霊験あらたか狛狐 | そもそものここが一丁目一番地 |
| 利根分水開削工事の水準点 | 夜夜中測量提灯ゆらゆらと |
| 提灯が流路の高低決めたんだ | 秋元公壮大な夢に科学あり |
| 新時代刀剣を置き手にするは | 戦国の堀切の技鍬と鋤 |
| 総社藩実り豊かに丁間台 | |
| まつりごといつの時代も先ず治水 | |
| 甲斐の国情けは味方仇は敵 | 激流の信玄堤に牛の角 |
| 海隔つ関東の華前橋城 | 名城も利根の激流抗えず |
| 秋元公暴れ川を鎮めんと | 用水路先鞭つけたにとどまらず |
| みずからの苦心の末の越中枠 | 利根川の取水口に据え付ける |
| 古写真に越中枠が列をなし | 領民と村の新田盾となり |
| 大海へ面舵一杯日本丸 | |
| 後の世も公の偉業を称えたり | 明治期に用水組合総代が |
| 長朝の事績に贈位を請願し | 県知事にあてた文書が世に残る |
| 長朝は越中枠を発明し | その構造簡易ながらも効果あり |
| 利根川が増水の時回転し | おのずから水門口を制御して |
| 水害の皆の患い無からしむ | |
 糸の町世界に広がる大航路 糸の町世界に広がる大航路 | |
| 空っ風氷のつぶてが突き刺さる | かしぐねは北面の武士仁王立ち |
| 強風にスクラム組むや長屋門 | 越屋根は七つの海の物見台 |
| 白い繭マイバシ世界を席巻し | |
| 秋元公平和な時代の礎を | 武器を捨ていくさなき世のおおいくさ |
| 領民と世界に開いた大航路 | |
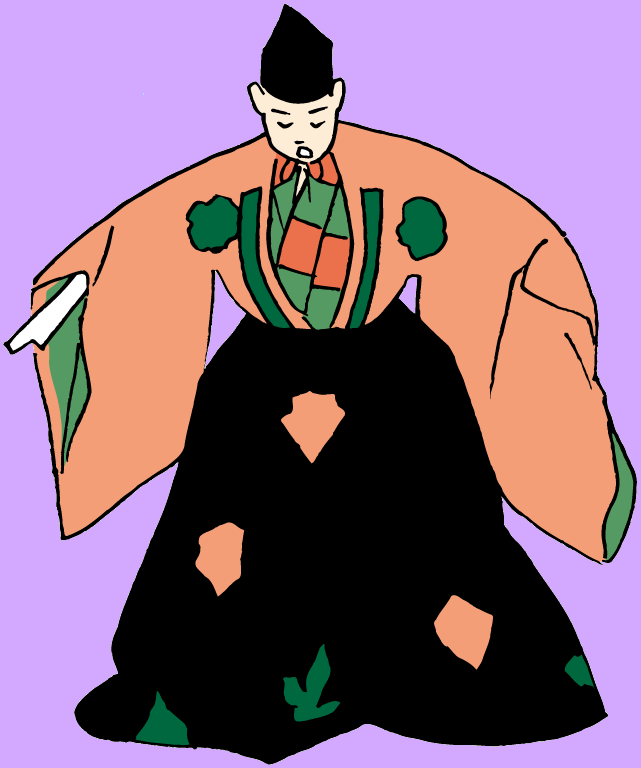 赤城山屏風一双榛名山 赤城山屏風一双榛名山 | |
| 利根川は難攻不落の堀なれど | 暴れ川敵に回せば恐ろしや |
| 騎馬隊の風林火山は既に無く | 着々と要地に広がる天下布武 |
| 名刹が厩橋城にほど近く | 三百歳シラカシの木を仰ぎ見る |
| 幽玄な蝋燭能が時を超え | 雅楽の笙今よみがえる長昌寺 |
| 戦国の騒乱の世を治めんと | 能舞台滝川一益演ずるも |
| 早馬が信長横死四方へ散り | 一益も京本能寺の変を知る |
| 都にて逆臣による謀反あり | 大乱にこうづけ諸将決起せよ |
| 他意あらばこの一益の首を獲れ | さもなくば迎え討とうぞ後北条 |
| 美しさ遡るほどに神流川 | |
| 奥多野を緑のダムに伏流水 | 深い森濾され真白き清流も |
| 白兵戦真っ赤に染まる神流川 | 鬨の声大地を揺るがす万の兵 |
| 激戦の無言の語り部河川敷 | 東国の覇者を争う大野戦 |
| 一益が本陣敷いた軍配山 | 円墳は平穏の世の象形か |
| 国道の喧騒よそに風の中 | 静寂にふたたび安堵の眠りつく |
| 麦秋の時は短しコンバイン | |
| 例幣使街道貫く玉村宿 | 北の国サイロの趣き銀の塔 |
| JAの群馬の小麦の大文字が | 雲のそば肥沃な大地の中に立つ |
| 麦秋の郷は命のファクトリー | 商用で過ぎ去るだけのこの道も |
| あらためて人の労苦に気づかされ | 玉村の滝川用水日に光る |
 慈眼寺のしだれ桜が舞う下に 慈眼寺のしだれ桜が舞う下に | |
| 天下人治水利水は国の基 | 江戸表河川改修大号令 |
| 関東は伊奈忠次を郡代に | 水利得て新田豊かに開発せよ |
| 代官は無理難題に嘆息し | 玉村は土地は平らで住みよいが |
| 平らゆえ水が流れていかんのじゃ | |
| 篤農家江原が妙案代官に | 上流の秋元公に願い出て |
| 堰広げ延伸したらいかがでしょう | 我が村も総社の村に倣いましょう |
| 農民も力合わせてやりまする | |
| 天目山武田滅びて遺臣散り | 身に付けた治水の技を世に広め |
| 慈眼寺のしだれ桜が舞う下に | 篤農家一命捧げた逆修塔 |
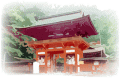 甲斐路より遺臣散じて世に尽くし 甲斐路より遺臣散じて世に尽くし | |
| 江戸古地図河川一本書き加え | |
| はるばると総社の村から水が来た | 頼朝公ゆかりの玉村八幡宮 |
| 数回の流路の失敗乗り越えて | 郡代の悲壮な決意が古文書に |
| 願わくば神霊我を祐けたまえ | 功成れば神社の造立以って謝す |
| 村の衆一間また一間と掘り進め | 延々と稲穂を見るまで丸五年 |
| 労働の辛さに汗を拭う時 | 青き峰赤城榛名に力湧く |
| 朱の色の成就の社殿遂に建ち | 村人も代官掘りと感謝こめ |
| 末永く伊奈と江原の名を刻む | |
| 古墳群古代に栄えた玉村町 | 時を経て滝川用水町めぐり |
| 平安期伊勢神宮の御厨が | 今の世にふたたび恵みの二毛作 |
 敷島にお艶観音松林 敷島にお艶観音松林 | |
| 何色と譬えも憚る松の苔 | カサカサとシャンソン歌い舞う落ち葉 |
| 秋色の観音像が笑み浮かべ | 身を投げたお艶が岩によみがえる |
| 淀君に寄り添う従者や黒い松 | 背に立って雨風凌ぐ松二本 |
| お艶とは実を申せば淀君なり | 夏の陣覚悟の自刃と伝わるも |
| 燃え上がる大坂城を脱出し | 弾幕下秋元陣に助け乞う |
| かねて聞く淀の美貌もやつれ果て | 長朝は悲運憐れみ駕籠に乗せ |
| 隠密に木曽路をひたすら総社へと | 大橋の局御艶と世を忍ぶ |
| 小谷城北ノ庄城大坂城 | 争いの世の儚さに苛まれ |
| 岩に立ち逆巻く利根に身を投ず | 村人は哀れ御艶よ安らかに |
| いつとなくお艶が岩と懐かしむ | |
 淀君が手づから植えた梅木増え 淀君が手づから植えた梅木増え | |
| 青き峰堰のしぶきよ都落ち | |
| 木曽路にて拾い上げたる梅の枝 | 総社へと落ちる道中離さずに |
| 淀君が手づから植えた梅木増え | 参道に枝を広げて人迎え |
| 苔むした墓に浅井と織田の紋 | 豊臣の駕籠の家紋を隠しつつ |
| 主なき引き戸や打ち掛け物悲し | |
| 関ヶ原用水開削夏の陣 | 労多く苦難の時代の拠り所 |
| 総社町植野に古刹元景寺 | |
 春めいて城もはなやぐ花衣装 春めいて城もはなやぐ花衣装 | |
| 信玄が苦杯なめたり箕輪城 | 謙信が兵を引いたり金山城 |
| 甲斐姫の出自をたどれば新田の地 | 豊臣軍何するものぞ気位は |
| つづら折り難攻不落の城にあり | |
| 類まれ武勇と美貌は敵に落ち | 敗軍の姫の胸中いかばかり |
| 領民と家名が残ればこの身など | 後ろ髪引かれながらも側室に |
| 忍城の城主家臣は助命され | 御三階櫓が凛と今も立つ |
| 伝え聞く醍醐の花見に歌を詠み | 短冊に可いの名前が残される |
| 武州去り春の京都の陽光に | 寂しくも穏やかな日が僅かでも |
| 気は晴れぬ花見の宴に淀君と | 言わずとも相身互いと意が通じ |
| 髪飾る花びら笑う野点など | 淀と甲斐二人の心の慰めに |
| 総社藩の領主秋元長朝は領民の暮しをいつも第一に考えていました。 領民は皆、秋元公の考えと施政を信頼していました。 秋元氏は二代三十三年間、総社藩を治めました。 五千石用水が今、総社の町を豊かに潤しています。 秋元公が総社に来る前はなかったことです。 領民はみんなで話し合いました。 水は自然に来るんじゃない、殿様の善政と努力のお陰だ。 感謝を込めて、後の世にこの素晴らしい事績を残そうじゃないか。 農民が一軒当たり一握りの米を出し合って、力田遺愛碑を建てました。 りょくでんいあいのひと読みます。 田につとめ愛を遺せし碑と、領主秋元長朝を称えています。 碑は1776年に建立されました。 秋元公の菩提寺の光巌寺にあります。 碑文の末尾には、百姓等建とはっきり書かれています。 ひゃくしょうらたてる 秋元公から受けた恩は石に刻んで残したい、農民たちの気持ちをよく伝えています。 身分の世にあっても、領主と農民の絆の強さが、また、互いに信頼し合っていた様子がわかります。 |
| 天狗岩用水は、遠く滝川用水へと延伸されました。 田を潤し、洪水を防ぎ、生活防火用水として活用され、村の環境が大きく改善されました。 さらには肥沃な農地を生み、二毛作の恵みまでもたらしてくれました。 総延長は22Km余りです。 代々の秋元家と総社の農民との絆は、秋元家の転封後も途切れることはありませんでした。 広範な地域で大きな飢饉が生じた、浅間山の天明の大噴火は1783年でした。 元景寺には噴火の犠牲者の供養塔があります。 甚大な被害を受けた総社の領民に、八代永朝は遠く山形から義援米を贈りました。 代々の秋元家の殿様も、総社の地を離れてもなお、苦楽を共にしてくれました。 |
| 長朝公の用水開削から400年以上にわたり、広い大地を潤し続けてきた歴史が評価され、 国際かんがい排水施設委員会より、天狗岩用水は世界かんがい施設遺産として、2020年に認定されました。 名君秋元長朝の善政と事績に感謝し、総社の地で総社秋元公歴史まつりが、秋に盛大に執り行われます。 |
