とも旗は命の起源海のブイ
里海や母なる海に畏敬の念

ⓒ石川県観光連盟
コロナ禍と能登半島地震により、中止が相次いだとも旗祭り。今年の5月には勇壮な船の渡御が行われました。地元の人たちにとって、この大きな大切な祭礼を、実はわたくしも楽しみにしていました。とにかく画像が素晴らしいですね。
20メートルもの大きなのぼり。そこには源平合戦を思わせるような力強い檄文が。
動画を止めて、目を凝らして文字を読みました。
“復興誓能登” “白湾興健児”
大きなのぼりは何百枚もの丈夫な美濃紙で作り、1枚1枚手作業で貼り合わせるそうです。大変な作業だと思いますが、これを地元の小中学生が中心となり、地域の人総出で準備するそうです。とも旗祭りは、もともとが子供さんが小さな船に旗を立て、それを伝馬船に見立てて遊んだことから始まったといわれます。
御座船を先頭に9隻もの船団。華麗な5色の吹き流し。笛や太鼓、鉦の音が空に抜けるようです。
能登の小木港は、イカ、鮭、鱒などの遠洋漁業で日本有数の港として知られていますが、一家の大黒柱が長期に家を留守にするわけですから、子供さんも寂しい思いをしたと思います。やはり、無事に帰って来てください、といった強い願いが込められていたと思います。
小木港は半島の内浦にあり、天然の良港といわれているそうです。古くは北前船の“風待ち港”としても活用されたとのことです。帆を高くあげ風を受けて疾走する北前船は、カッコいいですね。
私事で恐縮ですが、わたくしは波止場や桟橋の雰囲気、子供の頃は戦艦の模型などが好きでした。帆船がマストを高く掲げた写真など、自分には無縁な異国への航海を想像し、うらやましくも思ったものです。カラオケでは、“港町ブルース”が定番でした。
風待ち港っていう素晴らしいフレーズについ脱線してしまいました。
里山や田んぼの江を知る傘寿前

能登半島に稲作が伝来し、水田が開かれたのは弥生時代といわれます。さすが、大陸や朝鮮半島と一衣帯水の関係にある能登半島ですね。土器などのたくさんの遺跡があるそうです。歴史の長さもさることながら、能登半島の地形や海流など固有の環境により、稲作はじめ保存食などの特産品、祭礼などの独自の文化が、大切にはぐくまれてきたんですね。
田んぼの“江”(え)ということも勉強させていただきました。農作業の経験がある方にとってはご存知かと思いますが、わたくしは江を知りませんでした。
田んぼは稲の生育のために田植え後中干しをしますが、その際小さな生き物の生息場所として、田んぼの周囲に細い水路を作るそうです。いわゆる生物の多様性ということと、山側からの湧水を適度に集め、田んぼの地力を強くすることで、おいしい能登米が秋に実るといわれます。平野部が決して広いとはいえない奥能登で、手間を惜しまず、田を愛するがごとく、2000年もの労力のうえに成り立っているんですね。若干、自分に恥ずかしさも感じつつ、大切なことを教えていただき、ありがたく存じます。
広告
高田馬場の決闘
剣の才熱き心で江戸表 情厚く高田馬場で片肌に
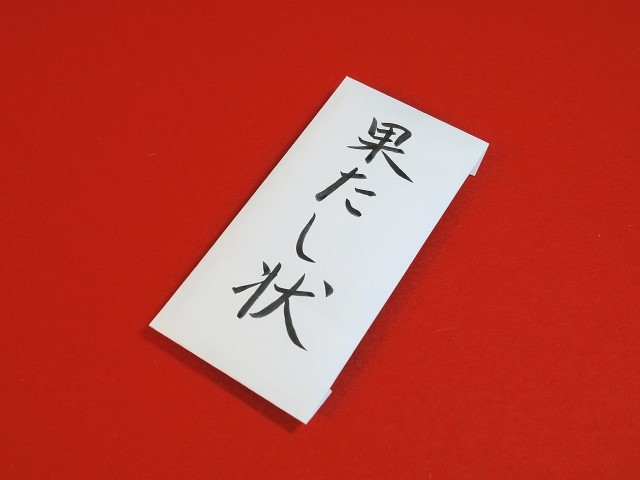
堀部安兵衛は越後の新発田藩に生を受けました。
幼いころに両親が亡くなり孤児になりますが、元禄元年(1688年)19歳で江戸に行きます。剣の腕前には天賦の才があり、小石川の道場でたちまち免許皆伝を授けられました。道場で叔父甥の契りを交わし、公私ともに親しくしていた伊予の藩士が、些細な口論から同僚の藩士と果し合いをすることになりました。叔父の藩士には2~3人の助っ人しか集まらず、相手方には6~7人もの、腕の立つ使い手が加勢しました。叔父は遺言代わりに、果し合いの後の始末を依頼しました。安兵衛は一も二もなく助太刀を承知しました。安兵衛の八面六臂の活躍により、3人の相手方を討ち果たしました。この噂は噂を呼び、江戸市中を駆け巡りました。既に、世は村芝居や小芝居が寺社の境内や橋のたもとなどで人々の人気を博していました。しまいには、安兵衛が倒した人数が、いつの間にか18人にもなるという過熱ぶりでした
それから数年後、安兵衛に惚れ込んだ赤穂藩の家臣、堀部金丸に婿養子に迎えられ、彼の運命が大きく変わることになります。
天からの陣中見舞いぞ牡丹雪
内蔵助枯れ木の山でなかりせば 快き死もあるべしと安兵衛に

以前は忠臣蔵のドラマが暮れになるとよくテレビで放送されましたね。
討ち入りの際、実際に人を切った経験がある義士は、四十七士のうち、安兵衛一人だけだったそうです。逆に彼は、吉良邸の守備の武士を一人も斬殺することはなかったそうです。「堀部武庸日記」等の文書によれば、「吉良方の家臣には遺恨なし、目指すは首級ただひとつ」という意味の言葉があるそうです。
安兵衛を急進派、過激派と評価する向きもありますが、彼のゆるぎない信念に敬服いたします。
討ち入り後、四家の大名家に預けられた義士たちは、元禄16年(1703年)2月4日、各屋敷にて切腹しました。
安兵衛は大石内蔵助の嫡男主税とともに、伊予松山藩の江戸屋敷にて生涯を閉じました。
艫となり安兵衛殉ずモミジ濃く


群馬県高崎市箕郷町に、箕輪城という堅城があります。遺構はよく整備され、巨大な空堀や土塁などが、その堅固な防衛力を物語っています。武田信玄が上杉軍との川中島の戦いを経て、天下の覇権を窺った戦国の世において、信玄の最強の時代でした。城主長野業正は西上州をよく統率し、何度も武田軍を撃退しました。その箕輪城の城下に、「旧下田邸書院及び庭園」があります。
12月の初め、紅葉も見納めと思い、女房も行ったことがないというので、行ってきました。書院の切妻は質実剛健、武家らしい佇まいです。女房は昔の建築様式に興味があり、庭から見られる欄間の透かし彫りに感じ入っていました。無駄のない、素朴さのなかの美しさというのでしょうか。
この庭園が、堀部安兵衛の指図によるものといわれています。高崎市吉井町に真庭念流の道場があり、そこで剣術を修行するかたわら、松やモミジを配置し、池をめぐる回遊式の庭園を造ったんですね。
師走になったというのに、モミジの木は名残を惜しむように赤々とした色を見せてくれました。
奥能登に春を告げ、遠洋漁業の無事を祈り、大漁を祈願する「とも旗まつり」は勇壮で美しいですね。
とも旗のともは艫と書くんでしょうか。
義を貫き、主君の無念を晴らした堀部安兵衛。
「旧下田邸書院及び庭園」で堀部安兵衛の影を、わずかながら感じられた日でした。


