のぼり旗藩主の願いを風に乗せ

御神木行き交う人馬の守り神
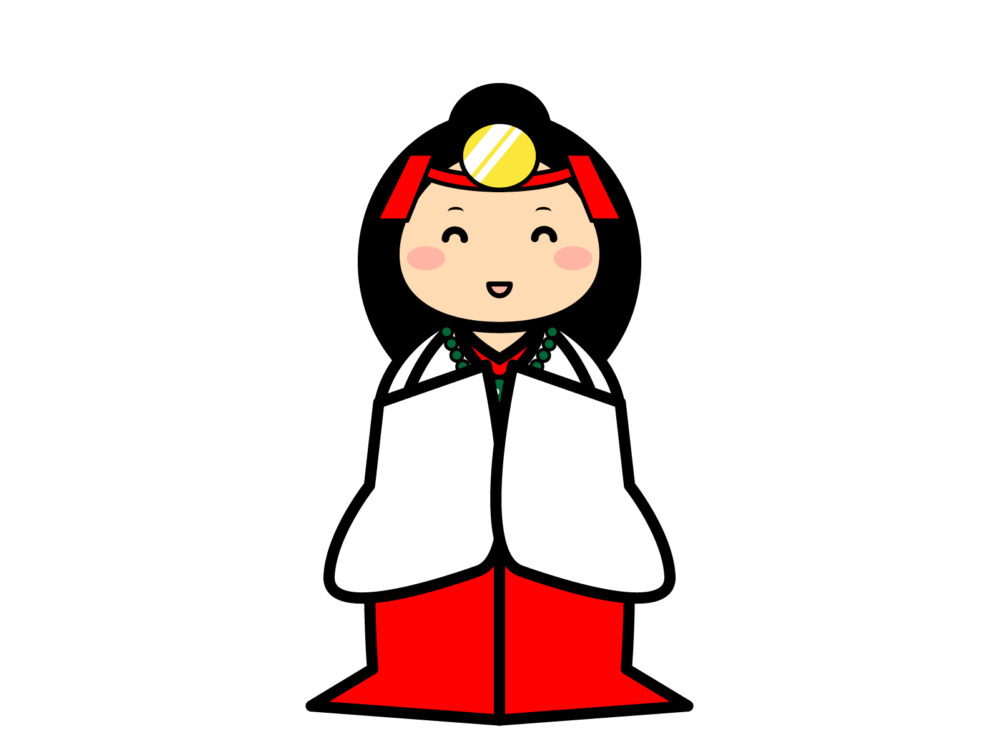
歴史に名高い本能寺の変。
家康公にも危機が迫りましたが、本国への生還が神君伊賀越えとして語り継がれています。
信長公の横死の知らせの際、家康公は大坂堺に滞在していたといいます。驚天動地の心境だったと思います。わずかな供回りと、伊賀越えにて本国三河を目指します。ひとつ間違えば命はありません。陸路は危険と判断し、伊勢国(三重県)から船で帰還することにしました。この時、船で救出に向かったのが、後に「汝に関東の華をとらす」といわれた、初代厩橋(前橋)藩主の酒井重忠公です。酒井家は以後9代、150年間にわたり、前橋の町割りを整備しました。前橋市紅雲町の龍海院に歴代藩主の墓所があります。徳川氏譜代の酒井家が、後に姫路に転封してからも、代々の藩主のお墓が、前橋の地を見守るようにそのまま残されています。
重忠公が巨石に稲荷大神を勧請して岩神稲荷神社と称され、以後巨石は公の思いを継ぐかのように、数百年にわたり、どっしりと鎮座しています。巨石の位置は交差点の西北にあたり、東西の幹線道路は交通量も多いです。交差する南北の道路が沼田街道です。この街道は沼田藩の参勤交代路でした。上杉謙信の関東出兵にも活用されたかと思います。軍道として、利根川流域の産物の交易路として、おおいに賑わったと思われます。南が前橋城方面になり、広瀬川が穏やかに流れ、なんとなく昔の城下町の風情が感じられます。
岩神稲荷神社の境内には、交通安全を祈願する御神木の榎が立っています。古木の貫禄で、行き交う人や車のドライバーの安全を、見守っているかのようです。
御分霊関東の華と共にあれ
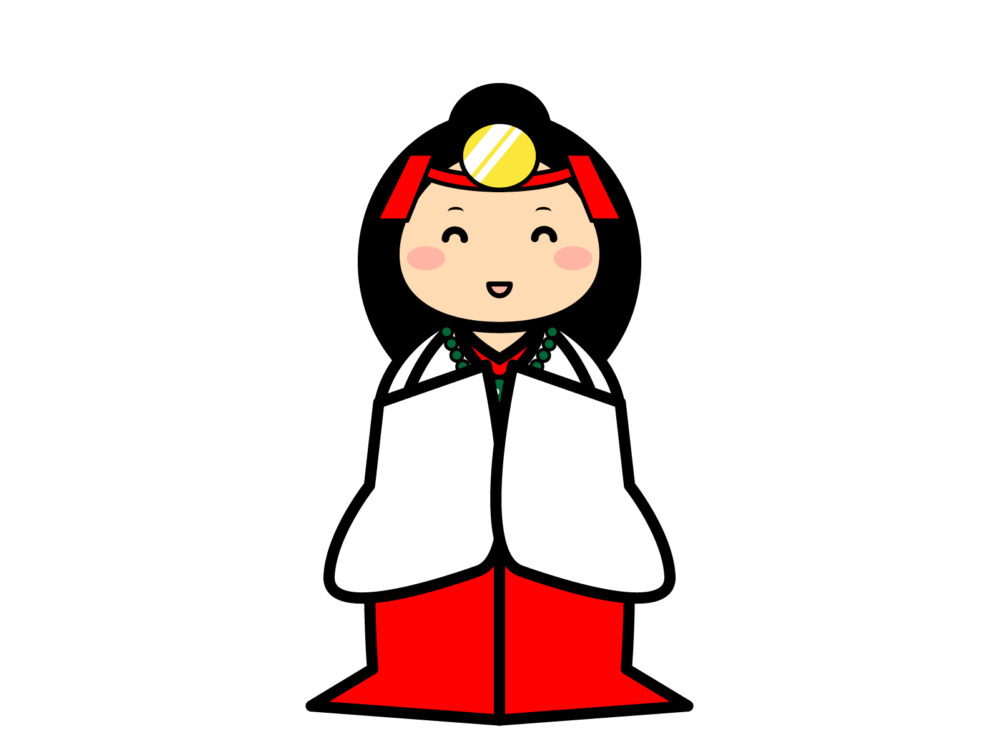
岩神稲荷神社の主祭神は、二つあります。
ひとつが、倉稲魂命(うかのみたまのみこと)です。
五穀豊穣、農耕の神であり、重忠公の民を思う心が感じられます。
時代は長い戦国の世が終わった直後であり、治世に携わる藩主も神仏に祈ることも多かったと思います。
近隣の総社藩の秋元長朝公も天狗岩用水の開削で、苦難の大工事をしていました。
境内にはたくさんのお狐様がいます。神社の狐は稲荷大神のお使いともいわれますが、豊年満作を願うばかりです。
もうひとつの祭神が、木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)です。
いい名前ですね。子宝、安産、子育ての女神でしょうか。
岩神稲荷神社の境内には、「乳銀杏」といわれる御神木もあります。
この御神木も樹齢を重ねた、見事な古木です。
農耕の神と子宝の神、初代前橋藩主の重忠公の切実な願いが伝わってきます。
神社の勧請とは、主祭神の分霊を新たに祀ることのようですが、全国等しく人々に幸せを届けていただきたいですね。

多摩川浅間神社

